スポンサードリンク
馴化-脱馴化法とは
馴化:継続してある刺激に触れ続けると、その刺激に慣れて、反応が減ること。
(例)時計の音、電車の揺れ、雨の音など。
脱馴化:馴化している状態で、新たな刺激を加えると、反応が復活すること。
(例)振り続けた雨が、一旦止んで、また降り出した時。
馴化ー脱馴化法とは、この2つの仕組みを利用して、特に乳幼児期の研究に利用されてきた。
- 乳幼児に刺激Aを与えて注意を向けさせる。
- 乳幼児に刺激Aを繰り返し与え、馴化させる。
- 乳幼児が刺激Aに馴化したら、刺激Bを与えて反応を見る。
これで、乳幼児が、与えられた刺激を識別できているかどうかなどを見ることができる。
第5回公認心理師試験に出題
乳児 50 名を対象として、視覚認知機能を調べる実験を行った。まず、実験画面上に図形 A を繰り返し提示したところ、乳児は最初は画面を長く注視したが、その後、注視時間は減っていった。注視時間が半減したところで、画面上に図形 B を提示したところ、乳児の画面の注視時間が回復して長くなった。一方、異なる乳児 50 名を対象として、 同様に画面上に図形 A を繰り返し提示し、注視時間が半減したところで、画面上に図形 C を提示した場合は、乳児の画面の注視時間は回復しなかった。この 2 つの実験結果から解釈される乳児期の視覚認知機能の性質として、最も適切なものを 1 つ選べ。
- 図形 C よりも図形 B を選好注視する。
- 図形 B には馴化し、図形 C には脱馴化する。
- 図形 B よりも図形 C に強い親近性選好を示す。
- 図形 A の後に、図形 C よりも図形 B の出現を期待する。
- 図形 A と図形 B は区別するが、図形 A と図形 C は区別しない。
解答
⑤
第3回公認心理師試験に出題
解答
⑤
スポンサードリンク
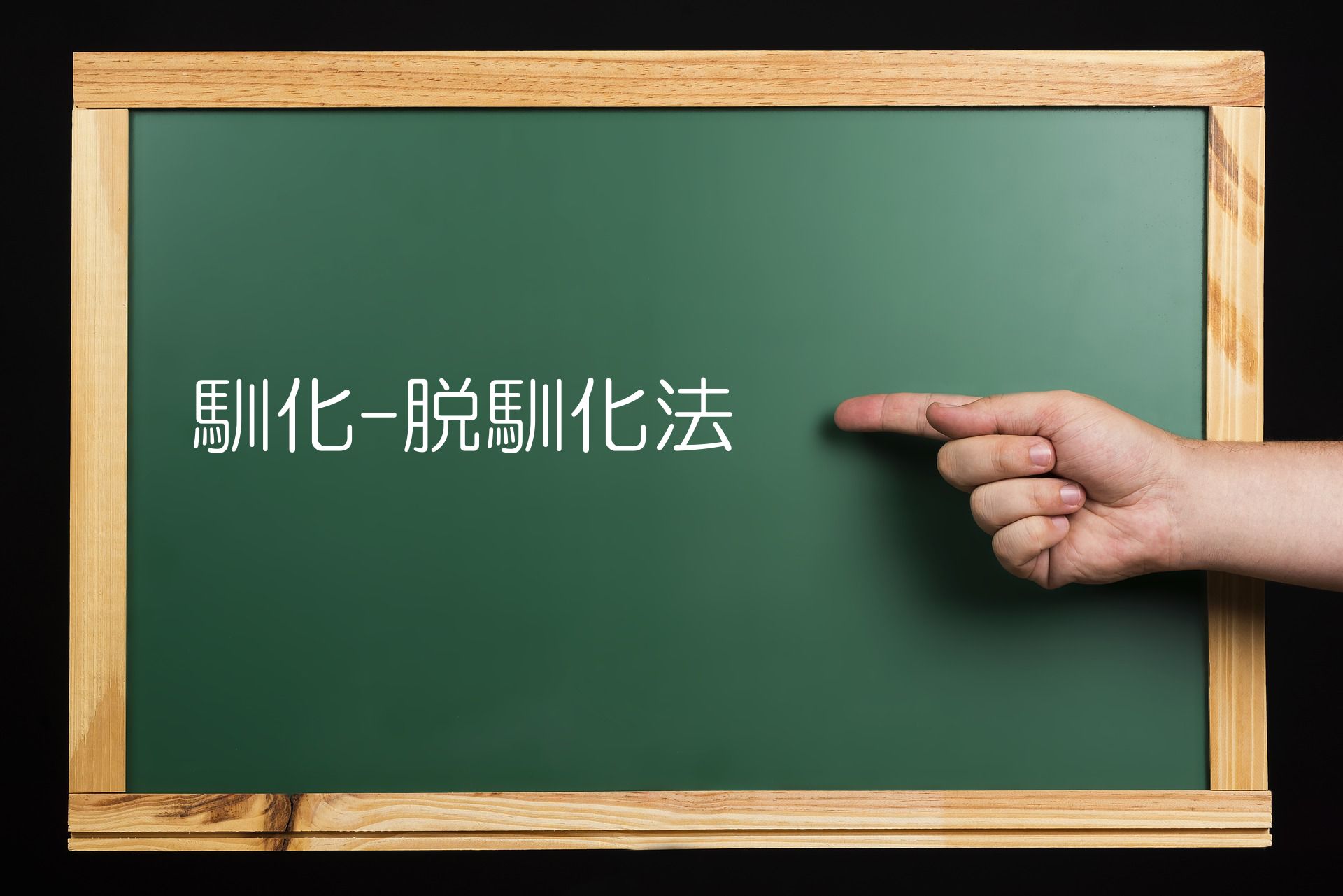





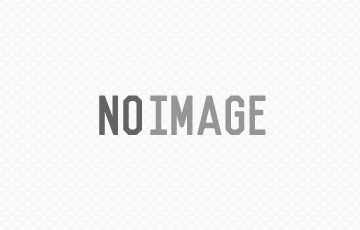


コメントを残す