スポンサードリンク[quads id=1]
問131 認知症について、正しいものを2つ選べ。
※採点除外対象問題
- Lewy小体型認知症は幻視を伴うことが特徴である。
- 前頭側頭型認知症は運動障害を伴うことが特徴である。
- 血管性認知症では歩行障害と尿失禁が早期から出現する。
- 若年性認知症で最も多いのはAlzheimer型認知症である。
- Alzheimer型認知症の早期には近時記憶の障害が見られない。
※採点除外対象問題
[/toggle]問132 注意欠如多動症/注意欠如多動性障害〈AD/HD〉の併存障害について、正しいものを2つ選べ。
- 環境調整と薬物療法とを考慮する。
- 成人期にはしばしばうつ病を併存する。
- 養育環境は併存障害の発症に関係しない。
- 自尊感情の高低は併存障害の発症に関係しない。
- 児童期には反抗挑戦性障害を併存することは少ない。
①については、不安障害などの併存障害について記載されているのか、ADHDについての対応について記載されているのか、文章だけでは読み取ることができないが、いずれにせよ、環境調整と薬物療法を有効である。
②については、成人期の併存障害として気分障害などが見られることが報告されている。
③については、不適切な養育環境(虐待や愛着の欠如等)で育つと、併存障害が生じやすい。
④については、自尊感情の高低は併存障害の発症に関係する。ADHDは、その特徴から叱責される機会も多く、学習面でのつまずきなどで、自尊感情が低くなりがちである。
⑤については反抗挑戦性障害を参照。診断基準に年齢の規定はない。またADHDの併存障害として反抗挑戦性障害はよく知られている。
[/toggle]問133 2型糖尿病について、正しいものを2つ選べ。
- ストレスは身体に直接作用して血糖値を上げる。
- うつ病を合併すると、血糖値は下がることが多い。
- 肥満や運動不足によってインスリンの効果が低くなる。
- 飲酒は発症のリスクを上げるが、喫煙は発症のリスクに影響しない。
- 薬物療法が中心になるため、服薬管理が心理的支援の主な対象になる。
詳しくは、2型糖尿病を参照。
[/toggle]問134 かかりつけの内科医に通院して薬物療法を受けているうつ病の患者を精神科医へ紹介すべき症状として、適切なものを2つ選べ。
- 不眠
- 自殺念慮
- 体重減少
- 改善しない抑うつ症状
- 心理的原因による抑うつ症状
DSMー5の大うつ病性障害の診断基準も参照のこと。すでにかかりつけの内科医のもとに通院している状況で、精神科医に紹介するということは、より危険で緊急性がある状態を考慮すると、やはり自死リスク。
そう考えると、②、④が妥当。
[/toggle]問135 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、正しいものを2つ選べ。
- 労働者はストレスチェックの受験義務がある。
- 精神保健福祉士はストレスチェックの実施者となれる。
- 全ての事業場でストレスチェックを実施する義務がある。
- 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を目的としている。
- 面接指導は、事業者に高ストレス者であることを知らせずに実施することができる。
労働安全衛生法、ストレスチェック制度を参照。
①全労働者が受験することがのぞましいが、受験義務はないため間違い。
②実施者は、医師、保健師および研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師である。
③常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務があり、それ以下は努力義務。
④未然防止で正しい。早期発見は高ストレス者。
⑤ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合は、事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を実施する。これのため、間違い。
[/toggle]問136 事例
新しい英語学習法の効果を検証するために実感計画を立てた。新しい学習法を実験群、従来型学習法を統制群とし、実験の参加申込順に最初の25人を実験群に、次の25人を統制群に割り当てることにした。各群にそれぞれの学習法を体験させ、4週間後にテストを実施することにしたが、この実験計画には問題点があった。
改善方法として、最も適切なものを1つ選べ。
- 参加者全体の人数を100人にする。
- 25人ずつ無作為に実験群と統制群に割り当てる。
- 学習法を実施する前にも、同様の英語のテストを実施する。
- 参加者全員に従来型学習法と新しい学習法の双方を実施する。
- 先に申込みがあった25人を統制群に、次の25人を実験群に割り当てる。
実験の参加者を申込にしているところを考慮しなければならない。参加申込順に実験群と統制群を割り当てることが問題。申込を早くする参加者は、実験や英語学習に対する意欲が高い可能性が考えられるため、ランダムで実験群と統制群に割り当てる方法を適用すると良い。
[/toggle]問137 事例
26歳の男性A、会社員。Aは仕事上のストレスが原因で心理相談室に来室した。子どもの頃から忘れ物が多く、頑固だと叱られることが多かった。学業の問題は特になかった。友人はほとんどいなかったが、独りの方が楽だと思っていた。就職した当初はシステムエンジニアとして働いており、大きな問題はなかった。しかし、今年に入って営業部に異動してからミスが増え、上司から叱責されることが多くなった。Aは「皆がもう少しゆっくりやってくれたら」と職場への不満を口にするが、「減給されるので仕事は休む気はない」と言う。
Aに実施するテストバッテリーに含めるものとして、最も適切なものを1つ選べ。
[toggle title=”解答”] ④子どもの頃の特徴やひとりが楽で営業部に異動してから問題が生じたという点。また「もう少しゆっくり」という主張からも、能力的な偏りがあり、人間関係が苦手であるということが推測される。
BACSは統合失調症、MMSEは認知症、STAIは不安(不安が主訴ならば適応を考慮)で今回は除外。知能検査で年齢的に適応されるのは、WAISであるため、④が正解。
[/toggle]問138 事例
36歳の男性A、会社員。Aは転職を考え、社外の公認心理師Bのカウンセリングを受けた。6ヶ月間BはAの不安を受け止め、二人で慎重に検討した後、転職することができた。初めはやる気を持って取り組めたが、上司が替わり職場の雰囲気が一変した。その後のカウンセリングでAは転職を後悔していると話し、AがBの判断を責めるようになった。次第に、Bは言葉では共感するような受け答えはするが、表情が固くなり視線を避けることが増えて行った。その後、面接は行き詰まりに達して、Aのキャンセルが続いた。
AがBの判断を責めるようになってからのBの行動の説明として、最も適切なものを1つ選べ。
- 不当にBを責めて、自分の責任を外在化するAに対して、距離を置いている。
- 不満をこぼすが状況に対処していないAに対して明確な姿勢をもって臨んでいる。
- それまでのようにAに支持と共感をしないことによって、意図せず反撃してしまっている。
- 誤った判断をし、Aを傷つけてしまったという不安が強くなり、介入することができなくなっている。
- 職場に対する不満の問題が再燃し、繰り返されていることを気づかせるために中立性を保とうとしている。
①は、キャンセルを続けてしているのはAであり、Bが距離を置いているわけではないので間違い。
②は、「言葉では共感するような受け答えはするが、表情が固くなり視線を避けることが増えて行った」という表現があり、Bは自己が不一致な状態であると言える。明確な姿勢をもって臨んでいるとは言えない。
④は、Bが転職をすすめるなどの判断をしたわけではない。また不安が強くなりというほど、不安の強さを表しているような記述もないため、不適当。
⑤については、②と同じく不一致な状態であるため、中立性を保つことができていないと言える。
[/toggle]問139 事例
15歳の男子A、中学3年生。Aは不登校と高校進学の相談のため教育相談室に来室した。Aはカウンセリングを受けることに対して否定的であった。「カウンセリングに行かないと親に小遣いを減らされるので来た。中学校に行けないことについてはもう諦めている。通信制高校に進みたいが、親が普通高校へ行けというので頭にくる。毎日一人で部屋で過ごしているのは退屈なので友達と遊びに行きたいが、自分からは連絡できない」と言う。実際には、中学校の生徒に見られることを恐れて、近所のコンビニにも行けない状態だった。
作業同盟を構築するためのカウンセラーの最初の対応として、最も適切なものを1つ選べ。
- カウンセリングがどのようなものかAに分かるように説明する。
- 通信制高校に合格すると言う目的を達成するために継続的な来室を勧める。
- Aと親のどちらにも加担しないように中立的な立場をとることを心掛ける。
- 外に出るのを恐れているにもかかわらず、教育相談室に来られたことを肯定してねぎらう。
- カウンセリングに行かないと小遣いを減らすと親から言われていることに「ひどいですね」と共感する。
どの選択肢も、カウンセリングにおいて、状況次第では間違った対応ではないと言える。しかし、今回は、カウンセリングに対して否定的で、まずは作業同盟を構築する、つまりカウンセラーとクライエントのラポールを構築することが大前提であり、その回答として最も適切なものは、クライエント自身の行動を肯定して労っている④が適当。
[/toggle]問140 事例
50歳の女性A、会社員。Aは不眠を主訴に病院に来院した。81歳の母親Bと二人暮らしである。Bは3年前にAlzheimer型認知症と診断され、要介護2で週3回デイサービスに通所していた。1ヶ月前から、Bは家を空けると泥棒が入り預金通帳を盗まれると言って自宅から出なくなった。さらに、不眠で夜間に徘徊し、自らオムツを外して室内を汚すようになった。Aは介護と見守りのためにほとんど眠れないという。
この時の病院の公認心理師がA及びBに助言する内容として、最も適切なものを1つ選べ。
- Aがカウンセリングを受ける。
- AがBと関わる時間を減らす。
- Aが地域活動支援センターに相談する。
- Aが介護支援専門員と共にBのケアプランを再検討する。
- Bが医療機関を受診し抗精神病薬による治療を受ける。
①Aの不眠は、Bの介護と見守りによるところが大きいため、カウンセリングよりも環境調整が必要であるため、不適当。
②関わり時間を減らすための、具体的なプランを必要としているため、助言としては間違っている。
③相談するのであれば、地域活動支援センターではなく、地域包括支援センター。
④「Bは3年前にAlzheimer型認知症と診断され、要介護2で週3回デイサービスに通所」と記載があり、状態が悪化してきたのは1ヶ月前。実際にはプラントは異なり、デイサービスどころか自宅から出ることができなくなっているため、ケアプランを再検討する必要がある。正解。
⑤Bの悪化した症状は、統合失調症などの精神疾患による妄想ではなく、認知症による被害妄想であると考えられる。医療機関を受診することは、必要になるかもしれないが、この時点で「抗精神病薬による治療を受ける」とまでは、到底断定できない。
[/toggle]スポンサードリンク[quads id=1]
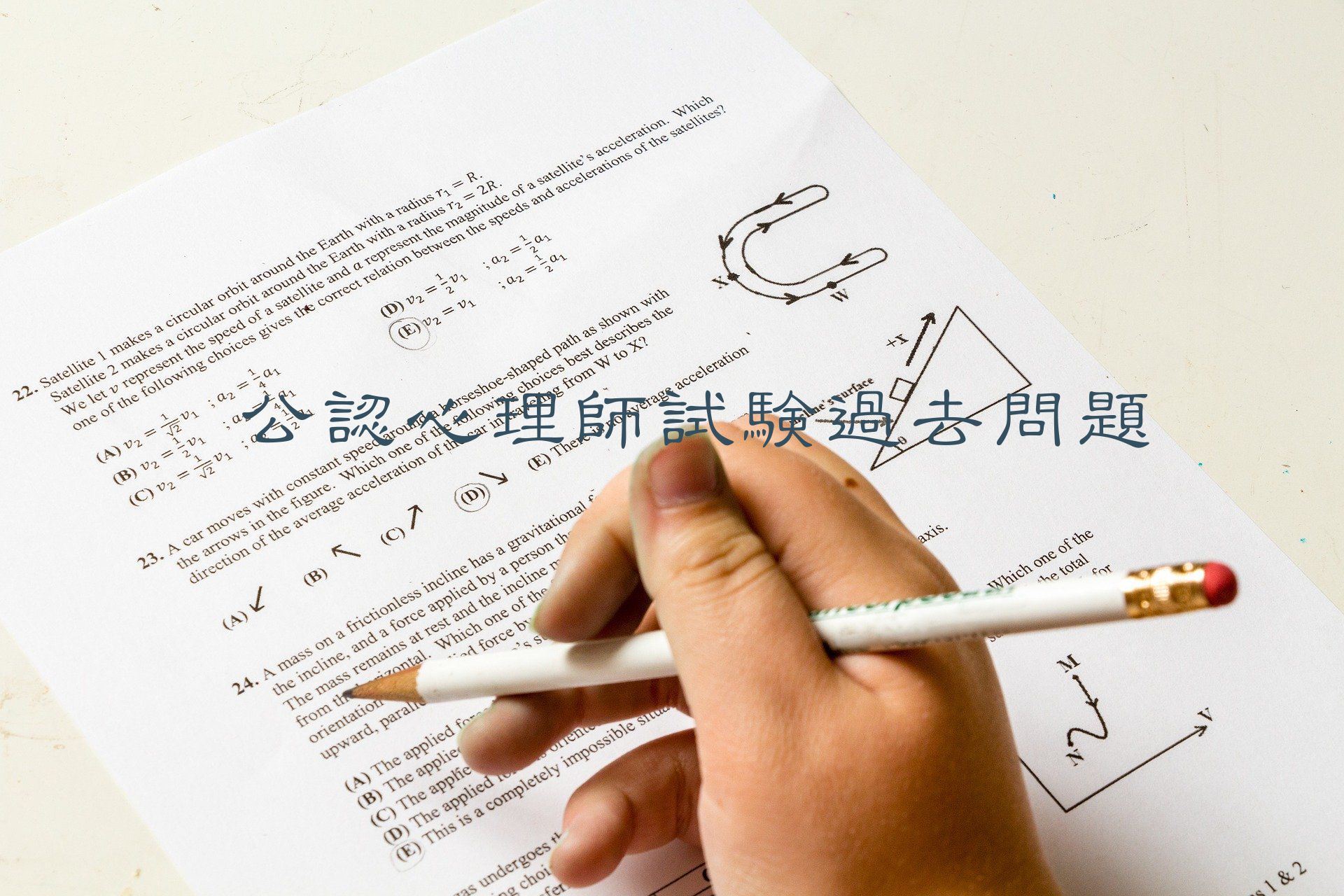


コメントを残す