スポンサードリンク[quads id=1]
Carl Ransom Rogers(カール・ロジャーズ)
クライエント中心療法を開発。アメリカ・イリノイ州生まれ。カウンセリング場面を録音したり、対話の仕方を実証的に研究しようとした。1950年代から日本に非常に強い影響を与える。
受容とはクライエント中心療法の、最も基本的な技法の一つで、相手の思いを受けとめること。
自己理論とは
自分が実際にできること、達成してきたこと(経験)と、自分の理想や目標(自己概念)が、自己一致しない時、人は不適応を起こすと考えた。
- 自己理論では,事実に則した自己概念をもつこと,すなわち「あるがままの自分」と自己概念とが一致することを目指す。決して、自己概念(理想や目標)に、あわしていくことではない。
- 自己一致を達成するためにカウンセラーが行うのがカウンセリングとなる
- ロジャースは、そのカウンセラーに求められる3つの態度を重視し、様々な技法を用いた。
《自己概念》
後天的に獲得された自己イメージ
《自己一致》
現実と自己概念が一致している状態
セラピーによるパーソナリティ変化の必要にして十分な条件(1957年)
人を変える6つの条件
第1の条件
2人の人が心理的な接触をもっていること。
第2の条件
第一の人(クライエントと呼ぶことにする)は、不一致(incongruence)の状態にあり、傷つきやすく、不安な状態にあること 。
第3の条件
第二の人(セラピストと呼ぶことにする)は、関係のなかで一致しており (congruent)、統合して(integrated)いること。
第4の条件
セラピストは、クライエントに対して無条件の肯定的配慮(unconditional positive regard)を経験していること。
第5の条件
セラピストは、クライエントの内的照合枠(internal frame of reference)を共感的に理解(empathic understanding)しており、この経験をクライエントに伝えようと努めていること 。
第6の条件
共感的理解と無条件の肯定的配慮が、最低限クライエントに伝わっていること。
援助者の3つの条件
第1の条件
自己一致(純粋性)
第2の条件
無条件の肯定的配慮
第3の条件
共感的理解
第5回公認心理師試験に出題
C. R. Rogersのクライエント中心療法における共感的理解の説明として、適切なものを2つ選べ。
- クライエントを知的に理解することではない。
- 進行中のプロセスとして保持すべき姿勢である。
- セラピストによって、言語的、非言語的に伝えられる。
- クライエントの建設的な人格変化の必要十分条件ではない。
- クライエントの私的世界と一体化することを最優先とする。
第4回公認心理師試験に出題
問9 C.R.Rogersのパーソナリティ理論の特徴として、最も適切なものを1つ選べ。
- 自己概念を扱う。
- 精神─性発達を扱う。
- パーソナリティ特性を5因子で捉えている。
- リビドーの向かう方向で内向型と外向型に分類している。
- パーソナリティ特性を外向─内向と神経症傾向という2軸で捉えている。
第1回公認心理師試験に出題
C.R.Rogersによるクライエント中心療法における共感的理解について、誤っているものを1つ選べ。
- 建設的な方向に人格が変容するために必要な条件の1つである。
- セラピストが共感的理解をしていることがクライエントに伝わる必要がある。
- セラピストの内的照合枠に沿って、クライエントが感じている世界を理解することである。
- クライエントの内的世界を「あたかもその人であるかのように」という感覚を保ちながら理解することである。
共感的理解は、無条件の肯定的配慮、純粋性(自己一致)とともに、セラピストに必要な基本的態度としたのが、C.R.Rogersによるクライエント中心療法である。共感的理解は、クライエントの内的世界を理解していくものであり、セラピストの内的照合枠に沿うのではない。
[/toggle]スポンサードリンク[quads id=1]

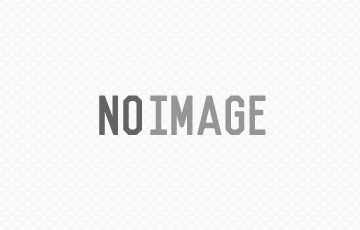

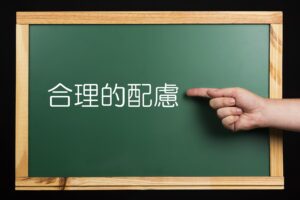
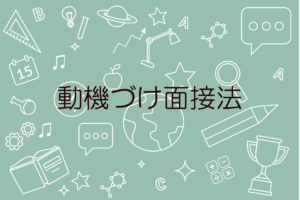
コメントを残す